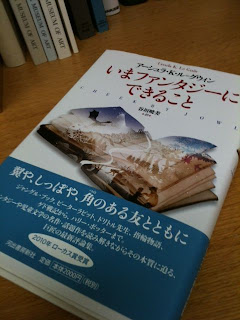『今ファンタジーにできること』
女房が孫にいろいろ本を買ってあげています。小さい頃にワクワクして読んだ本は一生の宝物のように思います。『今ファンタジーにできること』を読みながら、「文学の豊かさ」というものをあらためて感じています。
かつて『ゲド戦記』が宮崎ジュニアによってアニメ化されました。アーシュラ・K・ル=グウィンはその原作者です。今、彼女の名作の一つといわれる『闇の左手』というSFを読んでいます。もう一か月ほど寝床で少しづつ読んでいます。
この本(闇の左手)、半分までは数ページ読んでは眠くなり・・・だったんですが、半分を過ぎてからはがぜんおもしろくなり、今「物語」の醍醐味をたっぷりと味わっているところです。
私の定義「真の文学は読むのに時間がかかる」(いやそうじゃない、と云う人もいるでしょうが、個人的な経験から出した独断的な定義ですのであしからず。。。)
なぜ読むのに時間がかかるかといえば、想像力をかなり発揮しないと読めない、あるいは、言葉や文章一つ一つの含蓄� ��豊かすぎるからです。
それは、上等な容器に盛られた極上の料理だったり、上品な器にのせられた質素だが手の込んだあったかい料理だったり、ぱくぱく食べるにはもったいない食事にたとえられるでしょう。
思い起こせば、スタニスワフ・レムの作品だけを読んだ一年間もありましたし、山本周五郎だけの一年間もありました。
さて、そのル・グウィンのファンタジーに関するエッセーや講演録をまとめた『今ファンタジーにできること』を、ちょこちょこ読んでいるんですが、とても感動と納得があります。
数ヶ月前「ファンタジーの力」というブログでも紹介しました。
「物語(文学)」を通して「芸術の本質とは何か?」について大いに考えさせられます。
特に、「物語(文学)」を要約して理解したつもりになったり、物語そのものを体験せずに単にメッセージを探したりすることは無意味である、と指摘しているのは、文学すら「効率」という経済観念で処理しようとする私たちの宿病を指摘されているように感じ、恥じ入ってしまいました。
読書において、物語の主人公に自らなりきることと、他人事として高みから眺めることとはまったく異なることです。
ほんの少しつまみ食いで抜粋します。